今回は『気象の雑学』として、
2、なぜ起こる?
という2つの疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
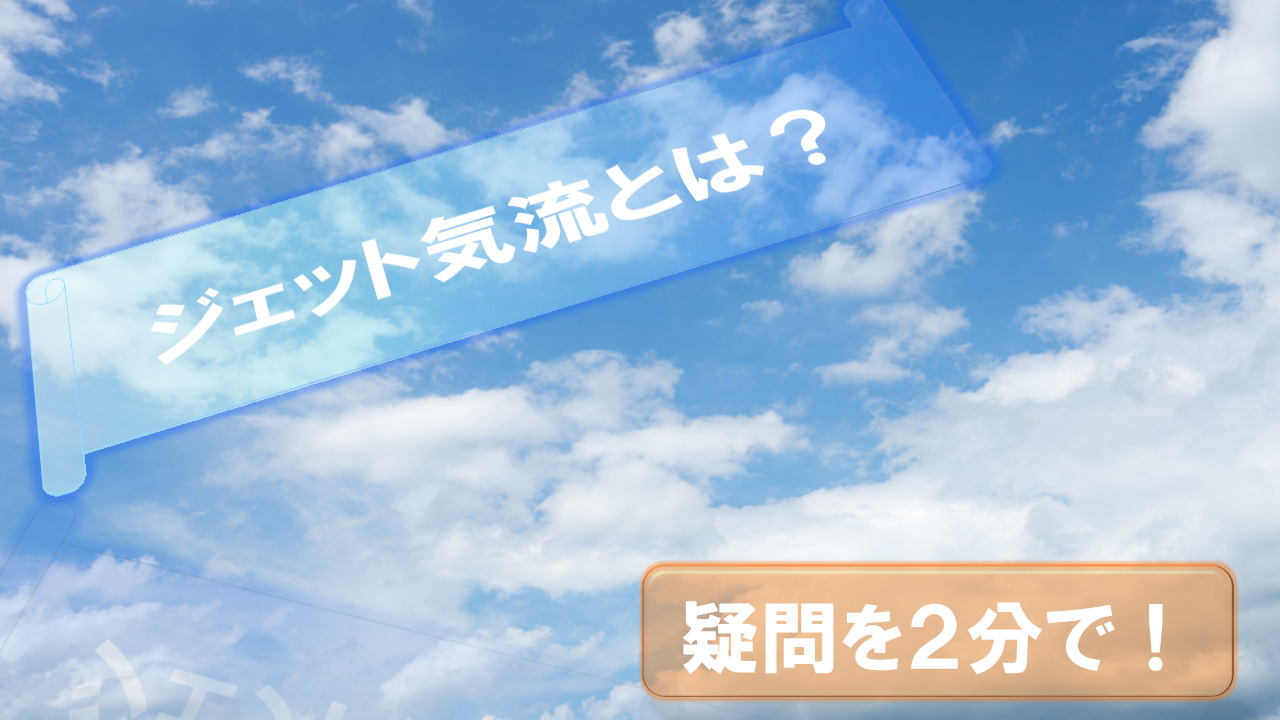
ジェット気流とは?|簡単に仕組み&原理
ジェット気流とは?|簡単に仕組み&原理
「ジェット気流」とは、ずばり
とても強く吹く【西】→【東】への風の流れ(= 偏西風)

のことで、「ジェット気流が発生する理由」は
空気がたくさん集まってくるから
気圧差が非常に大きいから
地球の自転によって進路が右側に曲げられるから(コリオリ力)

です。
スポンサーリンク
わかりやすく、もっとも身近な「ジェット気流」である
亜熱帯ジェット気流
※ 北緯30度(鹿児島あたり)、高度1万メートル付近で吹いている、風速20~100m/sを超える強い偏西風
を例に説明していきます。

というのは、ちょうど
① 赤道の暖かい空気が冷やされて地面に落ちてくる場所(ハドレー循環)
② 北緯60度付近(樺太より500kmほど北)で上昇した冷たい風が南下してくる場所(フェレル循環)

になっているため
空気がどんどん集まってくる場所(高気圧)
であり、かつ
2つの風がぶつかって地上に落ちてくる場所
でもあります。
集まった空気は
押し合いへし合いの【窮屈】な状態

になっていて
ので、「上空から地面に落ちた空気」はすぐに
していきます。
しかし、とくに
ために
地表の空気がすぐに暖かくなる
⇒ 軽くなった空気がどんどん上昇

⇒ 風に乗ってどんどん北上
してくるため、北緯30度付近では風を送って空気を減らしても
状況となり
になります。
このとき
には
地球が【西】→【東】方向へ自転をしていることによる力(コリオリの力)が加わる

ため
をとっています。
これが【西】→【東】に吹く偏西風が起こる理由です。詳しくは ↓ 参照。
よって
大気が不安定で気圧差が大きいことによる風の強まり
【西】→【東】へ加わるコリオリ力による偏西風
が重なることで
わけですね。
実際にはもっと複雑な大気循環メカニズムで、偏西風の一部がジェット気流になるというわけではないのですが、一般常識としては上記の流れを抑えておけば十分でしょう。
以上、『ジェット気流とは?|簡単に仕組み&原理』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
ジェット気流とは? ⇒ 強い偏西風のこと
なぜ起こる? ⇒ ① 空気密度の高まり|② 気圧差の高まり|③ コリオリ力による偏西風の発生