今回は『鳥の雑学』として、
という疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
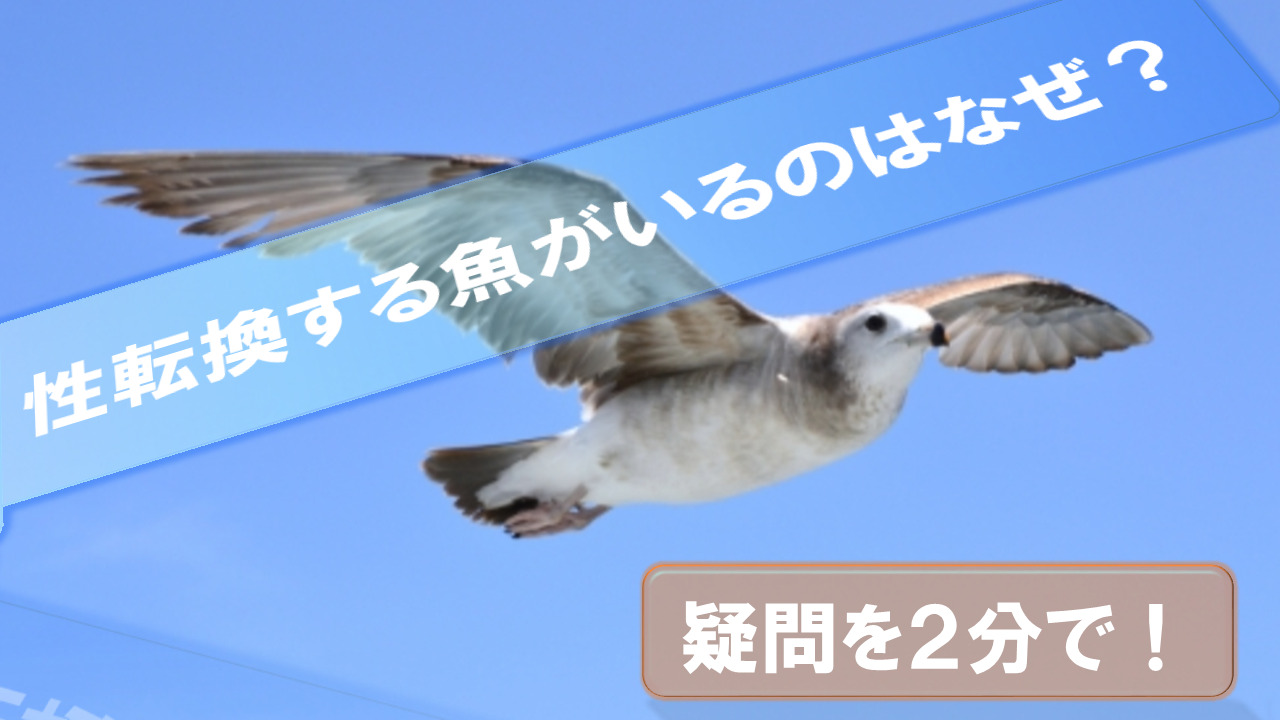
鳥はなぜ飛べる?|理由&仕組み
鳥はなぜ飛べる?|理由&仕組み
「鳥が空を飛べる理由・仕組み」は、ずばり
【骨】の中が空洞!
【排泄】がスムーズ!
【不要なもの】をなるべくカット!(オスがメスにアピールするためのディスプレイを除く)

飛行機と同じように【揚力(ようりょく)】を利用して上向きの力を得ている!
羽ばたく(下向きの)力で上に飛んでいるわけではないので注意!

の2つです。
スポンサーリンク
「鳥の骨」は
になっていて
ようにできています。

もちろん、そのぶんだけ
のですが、鳥は
ので大した問題にはなりません。
また、鳥には
ために
が備わっています。

「鳥の消化システム」は
ので少し難しく感じるかもしれませんが、ざっくりいえば
入ってきた食べ物に、強い酸性の消化液をかけまくる(腺胃による化学分解)
⇒ 柔らかくなった食べ物を、強い筋肉と砂粒で粉々にして急いで吸収(筋胃による消化吸収 ← 砂肝の部分)

⇒ 栄養が残っていようと構わずさっさと排泄
※ このとき、白いおしっこ(尿酸)もまとめて出すので鳥のうんちは下痢っぽくみえる
という感じです。

最後の
はかなりイメージしやすいと思いますが、
歯がない
膀胱(ぼうこう)がない
など、鳥は
です(歯がなくても砂嚢で消化は代用でき、また卵の孵化も早まると考えられます)。

ただその一方で
酸素交換を効率的に行う循環システム(二心房二心室)
複雑で大きく発達した飛翔筋肉
など
といえます(もちろん例外は多く、飛ぶことのできないダチョウやペンギンなどは上記とは性質がまったく異なります)。
「鳥が空を飛べる理由」でもう1つの大事な要素が
です。
よく
羽ばたくことで、鳥は上に飛びあがっているんだ!
と誤解されがちですが、実際には
飛行機と似たようなメカニズム

で
足と翼の先(初列風切)で前進することで【推進力】を得る
⇒ 翼の形によって空気の流れを下方向に変える(正確には翼後方上部の気圧を相対的に下げている)

⇒ 下がった気圧を埋めるために(空気を補填するために)翼の下から上に力が加わる(← これが揚力)
という仕組みです(逆にF1の車だと下向きの揚力で気体を地面に張り付けています)。

鳥の翼がなめらかなのは
で、逆にいえば
の場合では
ケースが多くみられます。
わかりやすい例でいえば
チョウやガのりんぷん


などはまさに力を受けやすくすることが主目的といって問題ないでしょう(付随して雨対策や繁殖オブジェクトなど)。
以上、『鳥はなぜ飛べる?|理由&仕組み』でした。
ご覧いただきありがとうございました<(_ _)>
鳥はなぜ飛べる?|理由&仕組み ⇒ ① 体がとても軽いから(骨の軽量化・排泄の特異化・不要物の排除)|② 前進することで揚力が得られる構造をしているから(翼後方上部の気圧を下げ空気の流れを下向きにすることで全体として上向きの揚力を獲得)※羽を上下させる風で飛んでいるわけではないので注意!