今回は『昆虫の雑学』として、
2、中身はどうなっている?
という疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
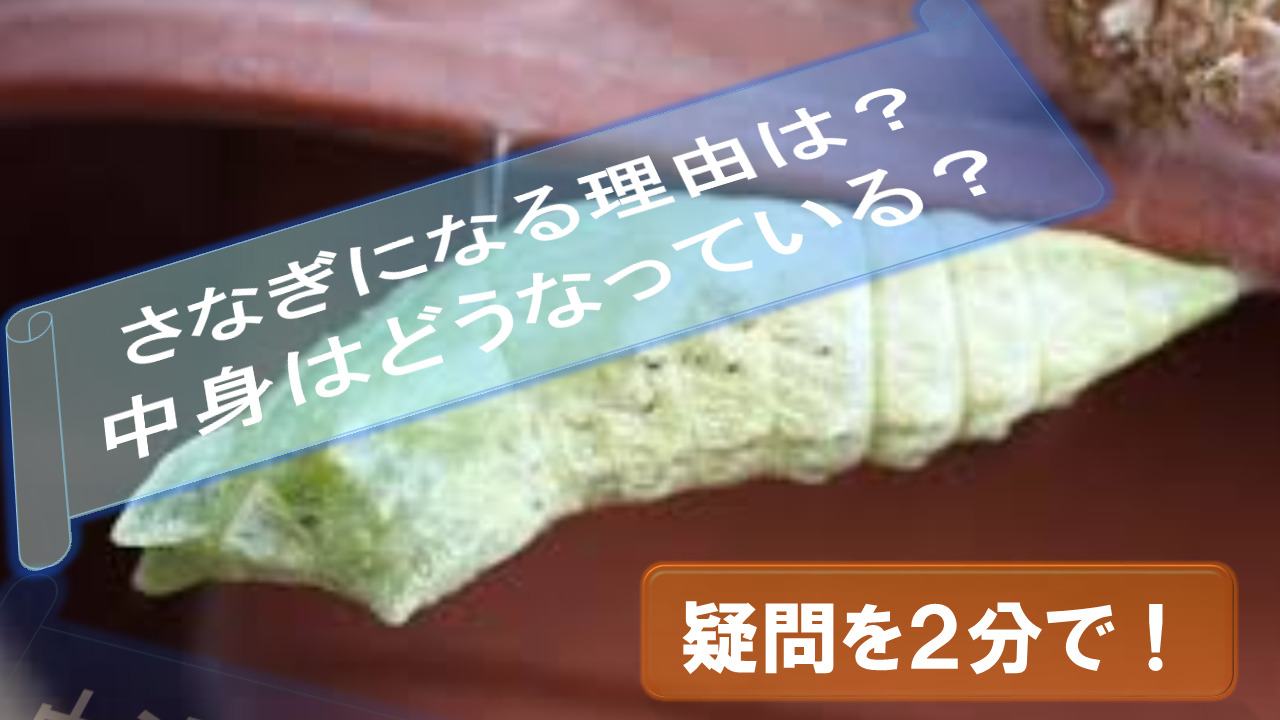
さなぎになる理由は?中身はどうなっている?
さなぎになる理由は?中身はどうなっている?
「さなぎになる理由」は、ずばり
幼虫のころはエサを食べることだけに集中して、さなぎの中で飛ぶ能力を一気に身につけ繁殖に特化した体にするため

で、「さなぎの中身」は
神経と呼吸器以外はドロドロに溶けている

と考えられます。
スポンサーリンク
「幼虫が成虫へと成長する方法」には
1、不完全変態(幼虫 → 成虫|バッタ、カマキリ、セミなど脱皮で成長)

2、完全変態(幼虫 → さなぎ → 成虫|チョウ、カブトムシ、ハチなど)

のどちらかの形をとる種がほとんどですが、「さなぎを経ることのメリット」として
ことが最も重要で
傾向にあります。

ただその代わりに
ため
ことから
と一般的にいえます。

なお
と思われがちですが、さなぎの状態では
ため
傾向にあります。

また、さなぎと聞くと
すると思いますが、実際にはさなぎを
や
の方が圧倒的に多いという点も一緒に覚えておいてください。

以上、『さなぎになる理由は?中身はどうなっている?』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
さなぎになる理由は? ⇒ 幼虫期に食べることに特化し効率的に成長するため
中身はどうなっている? ⇒ 神経系・呼吸器系以外はドロドロに溶けている