周期表シリーズ2本目の今回は、
『原子番号6,7,8,9,10ー炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、フッ素(F)、ネオン(Ne)』を紹介します。
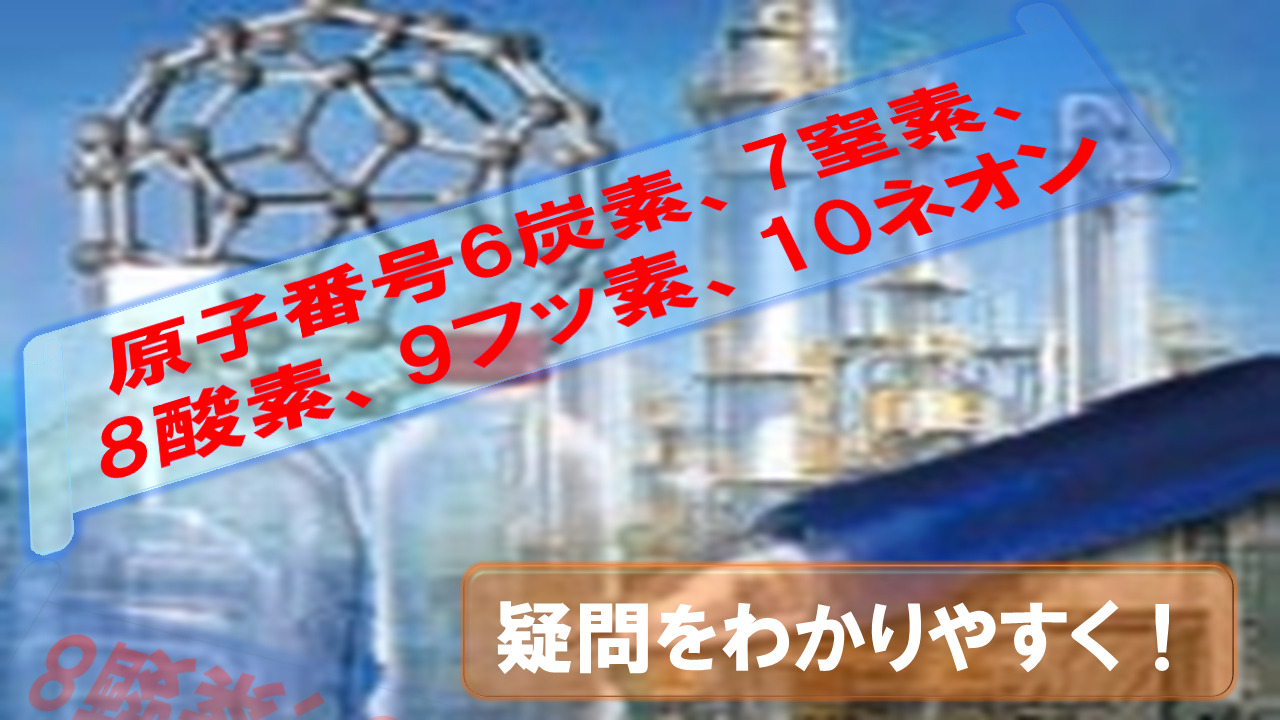
スポンサーリンク
原子番号6,7,8,9,10/炭素、窒素、酸素、フッ素、ネオン/特徴・性質・名前の由来
原子番号6 炭素(C)/特徴・性質・名前の由来
「原子番号6 炭素(Carbon)」の名前の由来は、ラテン語の「木炭(Carbo)」です。
炭素は生命体を作る基本元素である一方で、ダイヤモンドや黒鉛(グラファイト)としても有名ですね。
古くから木炭として利用されていた元素ですが、最近ではカーボンナノチューブに代表されるように、
テレビや自動車、宇宙線の材料などケイ素(Si:シリコン)にかわるエレクトロニクス素子としても注目されています。
炭素元素の大きな特徴として、炭素原子同士が結合した場合に非常に強い結合性を示すということが挙げられます。
例えば炭素原子が正四面体状に重なっていけばダイヤモンドとなり、すべての鉱物の中で最強の硬度を誇るようになります。
「硬度」というのは、傷がつきにくいという意味で壊れにくいという事ではありません。
ダイヤモンドもトンカチで叩けば簡単に壊れてしまいます。
このように、炭素分子だけでみた場合でも、構造の違いによって特性が大きく変わるため、非常に様々な用途に用いられます。
鉛筆や墨はもちろん、プラスチック、ゴム、ナイロンなど挙げていけばキリがありません。

原子番号7 窒素(N)/特徴・性質・名前の由来
「原子番号7 窒素(Nitrogen)」の名前の由来は、ギリシア語の「硝石(Nitre:しょうせき)から生じる(genes)」です。
窒素は空気中の体積比率が一番高い(約78%)ことが有名だと思いますが、
人体においても重量比で3.0%と欠かすことのできない元素です。
私たちの体を作るもとになる「アミノ酸」は窒素化合物で、このアミノ酸をもとにタンパク質が作られ、
タンパク質から筋肉だけでなく、酵素やホルモンなどヒトのほとんどの生体部品が作られます。
また、窒素分子が酸素や水素と比べて安定であるため、
窒素を液体化させ(液体窒素)、さまざまな試料の保存に使われています。
その他にも肥料の3要素であったり、石油化学工業や電子工業などで活躍するなど幅広い分野に必須の元素です。

スポンサーリンク
原子番号8 酸素(O)/特徴・性質・名前の由来
「原子番号8 酸素(Oxygen)」の名前の由来は、ギリシア語の「酸(Oxys)と生じる(genes)」です。
酸素は体内に最も多く含まれる元素です。
重量%でおよそ65%を占め、2位の炭素が18%なので大きく差を開けています。
地殻にも最も多く含まれていて(49.5%)、大気中では窒素に次ぐ2位です(21%)。
物が燃えるのも、鉄がさびるのも酸素原子が原因ですね。
生物には必須の元素ではありますが、原子の地球にはほとんど酸素がありませんでした。
植物という種が誕生し、光合成によって酸素が大量に合成され、その結果として十分なオゾン層が生成されたことで、
現在のような種の多様性がもたらされたと考えられます。
オゾン分子(O3)がなければ、有害な紫外線がそのまま降り注ぐことになり、遺伝的な進化を妨げていたことでしょう。
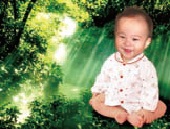
原子番号9 フッ素(F)/特徴・性質・名前の由来
「原子番号9 フッ素(Fluorine)」の名前の由来は、ラテン語の「ホタル石(Fluorite)」です。
化学の授業でよくフッ素を見たと思いますが、それはフッ素の反応性が非常に高いことに起因します。
原子番号の小さい希ガス(ヘリウムとネオン)を除けば、ほかのすべての元素と反応することができます。
そのせいでフッ素単体を分離することが難しく、初めて単離に成功したモアッサンにはノーベル賞が授与されました(1906年)。
フッ素の大きな特徴に、熱に強く水や油をはじく性質があるため、フライパンなどのフッ素樹脂でコーティングした商品は有名ですね。
その他にも歯の再石灰化を促進することから、歯磨き粉に含まれることもあります。

原子番号10 ネオン(Ne)/特徴・性質・名前の由来
「原子番号10 ネオン(Neon)」の名前の由来は、ギリシア語の「新しい(Neos)」です。
説明するまでもないかもしれませんが、夜の街に輝く「ネオンサイン」のネオンですね。
最近の若者は見たことがないかもしれませんが…。
ネオンは希ガスの1種で、非常に安定した元素です。
加えて、電圧をかけることで赤色に発光するのでネオンサインという明かりとして使いやすいわけです。
他の希ガスを加えれば、安全性を保ったまま色を変えることができます。
その他にもレーザー光や避雷塔に使われています。

以上、『原子番号6,7,8,9,10ー炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、フッ素(F)、ネオン(Ne)/特徴・性質・名前の由来』でした!
最後までお読みいただき、ありがとうございました<(_ _)>
「原子番号6,7,8,9,10ー炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、フッ素(F)、ネオン(Ne)」まとめ
原子番号6 炭素(C)/特徴・性質・名前の由来
・ 炭素は生命体を作る基本元素である一方で、ダイヤモンドや黒鉛(グラファイト)を構成している
・ 木炭のような使い道のみでなく、カーボンナノチューブというエレクトロニクス素子としても利用可能
・ 炭素原子同士が結合した場合に非常に強い結合性を示す(正四面体状に重なればダイヤモンドで最強の硬度)
原子番号7 窒素(N)/特徴・性質・名前の由来
・ 空気中の体積比率が最も高く(約78%)、人体の重量比でも3.0%と欠かすことのできない元素
・ アミノ酸は窒素化合物で、アミノ酸をもとにヒトのほとんどの生体部品が作られる
・ 液体窒素としての試料保存や、肥料、電子工業など用途はさまざま
原子番号8 酸素(O)/特徴・性質・名前の由来
・ 酸素は体内に最も多く含まれる元素(重量%で約65%)
・ 地殻にも最も多く含まれている(49.5%)
・ 光合成によって酸素が大量に合成され、オゾン層が生成されたことで多くの種が繁栄した
原子番号9 フッ素(F)/特徴・性質・名前の由来
・ フッ素の反応性は非常に高い(He、Ne以外のすべての元素と反応可能
・ 熱に強く水や油をはじく性質からフライパンのコーティング、歯の再石灰化を促進することから歯磨き粉に使用されている
原子番号10 ネオン(Ne)/特徴・性質・名前の由来
・ 希ガスであり非常に安定した元素
・ ネオンサインのネオン
・ 電圧をかけることで赤色に発光し、他の希ガスを加えれば変色可能