今回は『光の雑学』として、
という疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
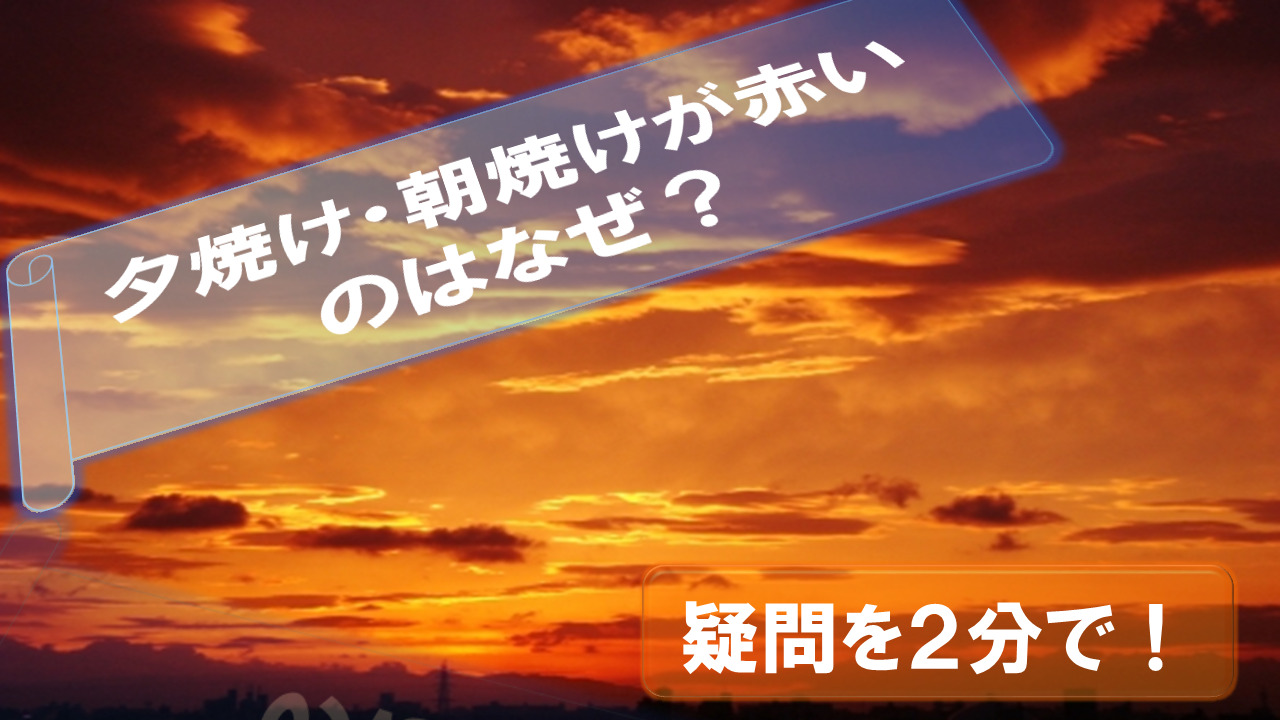
夕焼け・朝焼けが赤いのはなぜ?
夕焼け・朝焼けが赤いのはなぜ?
「夕焼け・朝焼けが赤い理由」は、ずばり「太陽光の中」の
【赤い光】は【空気の粒】にぶつかっても【散り散りになりにくい(散乱しにくい)】から
で、言い方を変えれば
です。
スポンサーリンク

「太陽光」は

されていますが、
波長の短い【青い光】は空気中の粒子にあたると強く散乱
空気中の粒子とは?:窒素・酸素などの【分子】&チリなど微小な【エアロゾル】
します(「レイリー散乱」といって「波長の1/10以下」の物質にあたると光は散り散りになり、「波長が短い」ほど強く散乱)。

そのため
昼 ⇒ 太陽が通る【空気の道】が短い ⇒ レイリー散乱した【青い光】が空全体を覆って青く見える

夕方 ⇒ 太陽が通る【空気の道】が長い ⇒ レイリー散乱によって【青い光】は失われ、残った【赤い光】が目立つ

ので
わけです。
関連記事
そのため、「夕焼け・朝焼け」でも
ことが多いと思います(ただし光量が弱いので暗い青にみえるはず)。

なお、知っている人が多いかもしれませんが
で、
があります(宇宙はぶつかるものがないから黒く見える)。

地表のあたりでは
している場合が多いのですが、大きな粒子にあたったときには
が発生します。

「夕焼け・朝焼けが赤い理由」に加えて、
レイリー散乱 ⇒ 小さい粒子(波長の1/10以下)にあたると発生!;波長が短いほど強く散乱!(波長の4乗に反比例)
ミー散乱 ⇒ 大き目の粒子(波長の長さ以上)にあたると発生!;波長が長さはあまり関係ない!
の2つも一緒に覚えておきましょう!(波長よりもっと大きい粒子には非選択的散乱が生じますがこっちは一般常識外なので覚えなくてOK)
以上、『夕焼け・朝焼けが赤いのはなぜ?』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
夕焼け・朝焼けが赤い理由 ⇒ 青い光がレイリー散乱によって遠くの空で失われ、残った赤い光がミー散乱によって目立つようになるから