今回は『空気の雑学』として
という疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
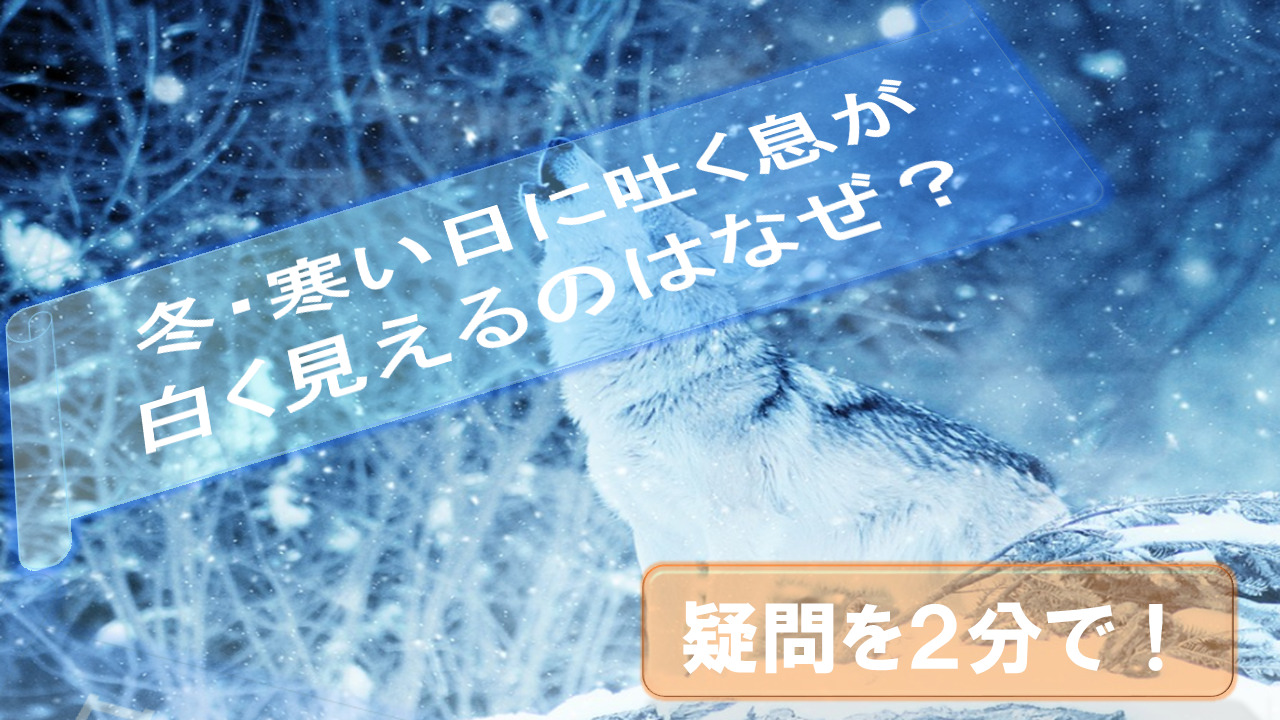
冬・寒い日に吐く息が白く見えるのはなぜ?
冬・寒い日に吐く息が白く見えるのはなぜ?
「冬・寒い日に吐く息が見える理由」は、ずばり
吐いた息がたっぷり含んでいる【水蒸気】が急に冷やされて【水滴】になるから(凝結:ぎょうけつ)
で、「白く見える原因」は
で、「息が見えるための条件」は
です。
スポンサーリンク

「空気中に含むことができる水蒸気の量」のことを
といいますが、「飽和水蒸気量」には
気温が低いほど小さい(水蒸気が少ししか存在できない)
気温が高いほど大きい(水蒸気がたくさん存在できる)
という性質があるため
息 ⇒ 33℃もあってたくさん水蒸気を含んでいる(飽和水蒸気量が大きい)
外の気温 ⇒ 寒いので水蒸気を少ししか含めない(限界を超えた水蒸気は水のつぶになる)
ことにより
というメカニズムです。

ちょうど
で、今回のケースでは
でしょう。
ちなみに
飽和水蒸気量が温度によって変わる理由(温度によって水蒸気の限界量が変わる理由)
は、いたってシンプルで
のことなので
温度が高い
→ 分子の運動エネルギーが大きいので、水分子が活発に動き回る
→ 水同士が引き合う力(分子による引力)を振り切って空気中に離散やすくなる
→ 水蒸気の量が増える
といったイメージで理解しておけば十分です(正確には大気圧・放射量・過飽和・過冷却など考慮すべき項はたくさんありますが、ざっくりした理解でOK!)。

以上、『冬・寒い日に吐く息が白く見えるのはなぜ?』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
冬・寒い日に吐く息が見える理由 ⇒ 息が含む水蒸気が急冷され水滴になるから(凝結)
白く見える ⇒ 水滴が光を非選択的に散乱するから
見える条件 ⇒ 温度差20℃以上が目安(息が約33℃なので外気温13℃以下で見えるようになることが多い)