今回は『エネルギーの雑学』として、
という疑問に、”わかりやすく・簡単に” 答えていきます。
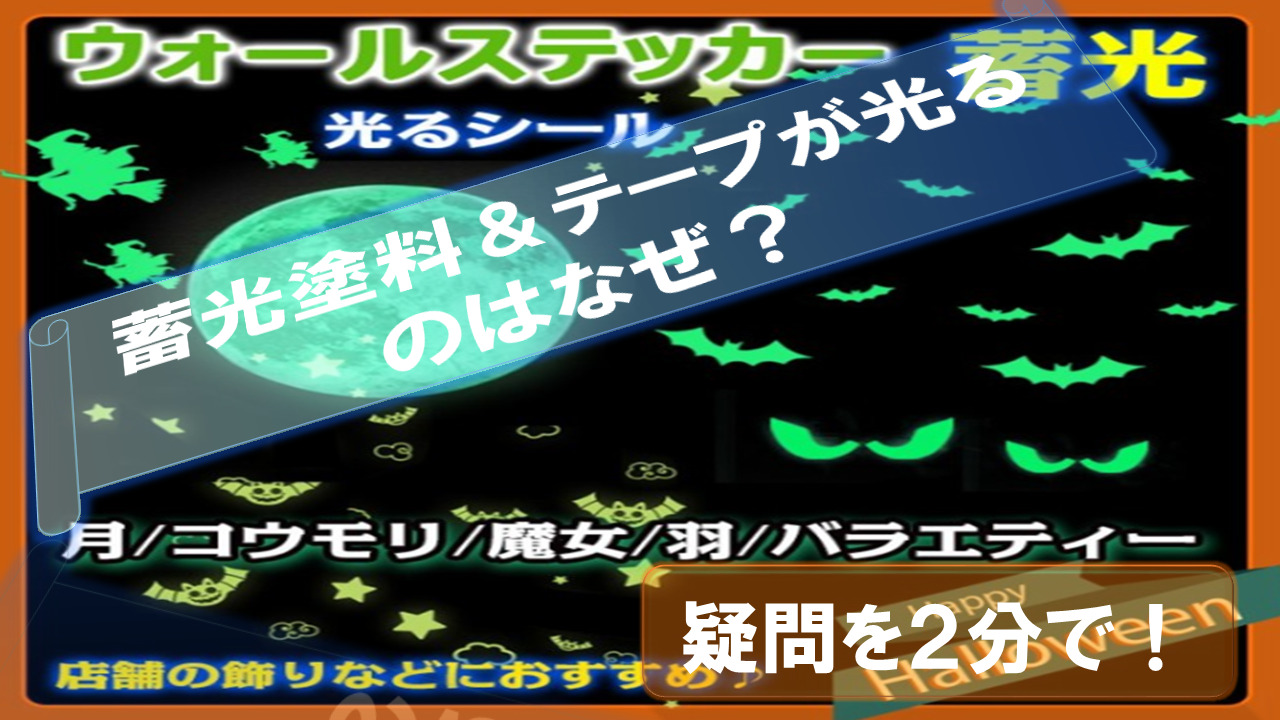
蓄光塗料・テープが光るのはなぜ?
蓄光塗料・テープが光るのはなぜ?
「蓄光塗料(テープ)が光る理由」は、ずばり
光のエネルギーをため込んで ”ゆっくり” 放出できるから
です。
スポンサーリンク

「蓄光する物質」として
が日本ではよく使われていますが、この化合物には
があります。

わかりやすくいえば
光があたるとエネルギーがUPする
※ 電子のエネルギーが高い励起状態(れいきじょうたい:高エネルギーで不安定な状態)になる
わけです。
こうした
のですが、蓄光物質ではさらに
光が当たらなくなるとゆっくりとエネルギーを放出していく
※ 時間をかけて基底状態(きていじょうたい:低エネルギーで安定している状態)に戻る
という性質があります。

そのため
に遷移するとき
されることで、視覚的には
ように見えるわけです。

大事なポイントは「蓄光塗料・テープ」が
で、蓄光商品が暗闇でもずっと光っていられるのは
だといえます。
ちなみに「蓄光」よりも「蛍光(けいこう)」という表現の方が馴染み深いかもしれませんが、厳密には
で、
蓄光 ⇒ 光をたくわえて放出
蛍光 ⇒ 光を強く反射

という感じで
ます。
ただ、蓄光商品を蛍光と呼んでいる例は多く、蛍光の化学的定義としては励起状態を介した発光現象であることは確かなため一般常識としては明確に区別する必要はないでしょう。
(念の為正確に説明しておくと、蛍光は基底状態への遷移が速く発光時間が短いもの、蓄光・燐光は遷移が遅く発光時間が長いもので量子力学的なプロセスはまったく別;化学を専攻している学生は総スピンから厳密に区別しておく必要あり)
以上、『蓄光塗料・テープが光るのはなぜ?』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
蓄光塗料・テープが光る理由 ⇒ 光を吸収して、ゆっくりと蓄えたエネルギーを放出しているから